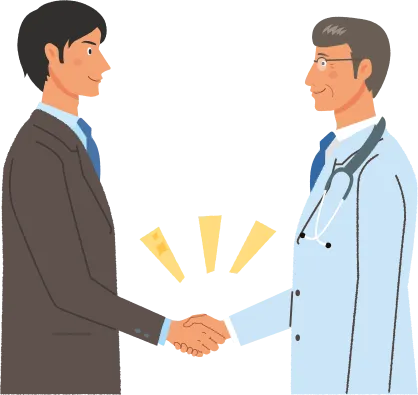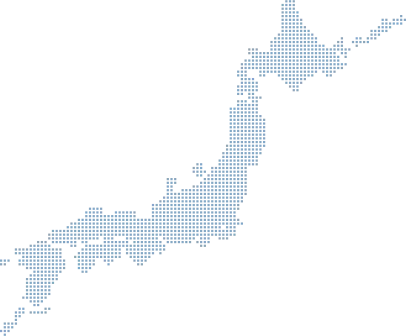B型肝炎給付金請求を行う弁護士事務所
HEPATITIS
B型肝炎給付金請求訴訟は、集団予防接種による注射器の使いまわしで感染被害を受けた方々が、国から適正な補償を受けるための手続きです。手続きを円滑に進めるには、法的な専門知識と経験が求められます。申請から給付金受領までをサポートし、少しでも早く給付金を受け取れるよう尽力いたします。訴訟に関するお悩みや疑問があれば、安心してご相談いただける環境を用意しています。
お問い合わせ・無料相談はこちら
給付金額
BENEFIT AMOUNT
B型肝炎感染者の方への給付金額は50万円から3,600万円です
給付を受けることができる方
CHECK
以下の項目に1つでも該当する方は、給付を受け取れる可能性があります。いくつ当てはまるか、チェックしてみましょう!
一次感染者 | ・昭和16年7月2日〜昭和63年1月27日生まれの方 ・血液検査(献血含む)の結果、B型肝炎ウイルスに持続感染 ・満7歳の誕生日の前までに集団予防接種またはツベルクリン反応検査を受けている ・集団予防接種等以外の感染原因がない |
|---|---|
二次感染者 | 一次感染者である母親または父親からの母子(父子)感染により持続感染者となった |
その他 | 一次感染者または二次感染者の相続人 |
1つでも該当する方は給付を受けることが可能!
1つでもチェックがついた方はお問い合わせください!
通常費用オールゼロ完全成功報酬制
報酬額は実質7%
成功報酬は、お客様の受ける給付額の実質7%(国が負担する4%と合わせると11%)です。
ただし、無症候性キャリアについては定額11万円(税込み)とします。
他の事務所と比較し極めて低廉ですが、訴訟対応は丁寧で手抜きがありません。
相談料:0万円
着手金:0万円
調査費用:0万円
印紙代・切手代、裁判費用:0万円
広告・宣伝費の不支出、説明会などの不開催、案内や資料作成の省略などの徹底したコスト削減により、
弁護士報酬の低廉化、通常費用オールゼロ、完全成功報酬制を実現しました!
医療過誤訴訟・集団訴訟での
経験と専門的知識の活用
B型肝炎訴訟では、案件により、医学的知識や医学的証拠の収集力が重要となります。当事務所の弁護士は多くの医療過誤案件を処理しており、弁護士が協力医と連携して培った医療裁判の経験を通じ、医学的知識、医学的証拠の収集方法に精通しています。カルテの解読、分析などから培われた経験やノウハウはB型肝炎訴訟においても強い武器となります。
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が規定する慢性肝炎や肝硬変に該当するかどうかは、医師と協力しながらカルテを丹念に分析しなければ判断することができません。例えば、現時点で慢性肝炎ではないと診断されている場合でも、カルテを分析することで慢性肝炎として提訴する可能性が出る場合があります。
当事務所では、医療に強い弁護士が協力医と相談しながらカルテを分析することで、お客様に適切な給付金をお受け取りいただけるよう努力しております。
肝臓疾患に強い医師の協力により、随時、医学的知識についての補足、医学的資料の収集をサポートしてもらえる体制が取られています。
B型肝炎訴訟でも、このような医療過誤訴訟、集団訴訟での経験と専門的知識を活用できるのが、当事務所の強みです。
手続きの流れ
FLOW
無料相談
STEP01
B型肝炎給付金に関するご相談は、何度でも無料でお受けしております。
お申し込み
STEP02
相談後、当事務所から、「申込書」と「基本事項の確認シート」をお送りしますので、必要事項を記載していただき、お手持ちの関係資料とあわせてご返送いただきますと、担当弁護士等がご依頼者様の状況を分析し、今後の流れや資料収集などについて、具体的かつ丁寧なアドバイスをいたします。
調査・資料収集
STEP03
病院等から必要な資料の収集をお願いいたします。重要な資料から順番に収集し、ご依頼者様の負担軽減と効率的な収集を実現します。収集した医療記録や血液検査の結果などの資料を分析し、提訴可能か否かを診断します。提訴が可能な場合には、裁判に移行します。契約書、委任状に署名・押印し、お送りいただきます。提訴可能ではない場合には、サービスは終了となります。
訴訟提起及び裁判所での和解手続き
STEP04
担当弁護士が、収集した資料をもとに裁判所に訴訟を提訴します。担当弁護士が、B型肝炎給付金の受給について国と和解協議を行います。和解協議がまとまると、和解が成立します。和解協議がまとまらない場合には、和解は成立しません。
支払基金への給付金請求・受取り
STEP05
裁判所は、和解が成立すると和解調書を作成します。当事務所が和解調書を受け取り、社会保険診療報酬支払基金に請求し、給付金の支給を受けます。
お支払い
STEP06
当事務所が弁護士費用を差し引き精算を行い、ご依頼者に給付金をお支払いします。
必要書類
REQUIRED DOCUMENTS
B型肝炎訴訟は感染状態の違いにより立証するために必要な書類が変わります。
必要な書類は下記のとおりですが、感染者の病態などケースにより異なるので、具体的にはご相談の際にご説明いたします。
一次感染者の場合
条件:B型肝炎に持続感染していること
・HBs抗原、HBV-DNA、HBe抗原のいずれかの値が、6か月以上間隔をあけた2時点において陽性である場合
・HBc抗体が高力価陽性である場合
以上の2つの条件のうち、いずれかを満たす場合が「持続感染」に該当することになります。
・1の要件では、6か月以上間隔をあけた2時点での検査結果が必要(つまり、2回の検査が必要となります)となります。
・2の要件では、1時点の検査結果(つまり、1回の検査)で足ります。
これらは、血液検査または医療記録をもとに立証することになります。なお、HBc抗体が高力価陽性とは、基本的には、CLIA法で10.0以上の値が出た場合をいいます。
立証1:7歳までに集団予防接種等を受けていること
・母子手帳
B型肝炎訴訟における「7歳までに集団予防接種等を受けていること」という条件は、予防接種を受けたことの記載がある母子手帳によって立証することになります。
母子手帳が残っていない場合
基本的には下記の資料を提出して立証することになります。なお、母子手帳に予防接種を受けたことの記載がない場合もこちらの方法で立証することになります。
陳述書:予防接種に関する陳述書と母子手帳に関する陳述書の2種類の陳述書を提出することになります。
接種痕が確認できる旨の医師の意見書:こちらは、BCGや種痘の痕が残っていることを医師に確認してもらって作成する意見書になります。
住民票または戸籍の附票:3の住民票または戸籍の附票が地方自治体によって廃棄されてしまっている場合は、別の資料を提出する必要がある場合があります。
個々のケースによって必要な資料は異なりますので、詳しく知りたい場合には、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
立証2:母子感染でないこと
B型肝炎訴訟において、母子感染ではないことという条件は、基本的には、下記を示す資料を提出することで立証することになります。
・母親のHBs抗原が陰性でかつHBc抗体が陰性(または低力価陽性)
・母親が死亡している場合は母親が80歳未満の時点でのHBs抗原陰性
・年長のきょうだいのうち一人でも持続感染でない者がいること
母親がご存命の場合は、血液検査をして頂き、1の要件が満たされているかチェックします。なお、ここでの低力価陽性とは、一般的には、CLIA法で10.0未満の値であった場合をいいます。母親が亡くなられている場合は、医療記録から80歳未満の時点でHBs抗原が陰性であった血液検査を探し、これをもって立証することになります(要件2)。母親が亡くなられており、80歳未満の時点での血液検査結果もない場合には、要件3で、年長のきょうだい(自分にとって兄か姉)に血液検査をして頂き、HBs抗原が陰性でかつHBc抗体が陰性(または低力価陽性)の結果がでれば、当該血液検査結果で立証することになります。
二次感染者の場合
前提:二次感染者(子ども)が請求をする前提として、まずは一次感染者(母親)が給付対象となる必要があります。
条件:
二次感染者が請求する条件は以下の通りです。
・母親が一次感染者の要件を満たすこと
・子どもがB型肝炎ウイルスに持続感染していること
・母子感染であること
母子感染であることは、どのようにして立証するのでしょうか?B型肝炎訴訟では、母子感染した場合の子も二次感染者として給付金の対象となります。母子感染であることという要件は、具体的には、下記のいずれかの資料を提出することで立証することになります。
・原告が出生直後に既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料(※1)
・原告と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果(※2)
※1の資料は、子どもを出産した病院の医療記録に記載されていることが多いです。
※2の資料は、母親と子どものウイルスを比較する検査になります。こちらは対応してもらえる病院がそう多くないため、検査をする場合には弁護士に相談してください。
このほかに、下記の資料があります。
・子どもの出生前に母親の感染力が弱かったこと(HBe抗原が陰性であったこと)が確認されないこと
・子どもが昭和60年12月31日以前に出生していること
・医療記録等に母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
・父親が持続感染者ではないか、または父親が持続感染者であっても子どもと父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されないこと
・子どものB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeでないこと
上記の要件を示す資料を提出することで立証することも可能です。この方法の特徴は、母親と子どもの塩基配列検査をする必要がないという点にあります。塩基配列検査は高額になる場合が多く、これを避けるために上記方法で立証することもあり得ます。
その他の場合
上記の相続人の場合は、戸籍謄本や場合により遺産分割協議書等が必要となることがあります。事案により異なりますので、適宜、連絡させていただきます。
学歴 | 早稲田大学法学部卒業 |
|---|---|
職歴 | 東京地方検察庁検事 釧路地方検察庁検事 東京法務局訟務部付検事 法務省訟務局付検事 札幌法務局訟務部付検事 大阪地方裁判所判事 盛岡地方・家庭裁判所判事 仙台高等裁判所判事 仙台法務局訟務部長 東京家庭裁判所判事 仙台家庭裁判所上席判事 平成20年弁護士登録 |